
CASE STUDY
事例紹介
これまでに約20の業界、毎年数百件の
コンサルティング実績を誇ります。
企業規模や特定の業界に限らず、人事領域の課題を包括的な解決策を提供したこれまでの実績をご紹介します。
©️ Transtructure Co.,Ltd.All Rights Reserved.
©️ Transtructure Co.,Ltd.All Rights Reserved.



これまでに約20の業界、毎年数百件の
コンサルティング実績を誇ります。
企業規模や特定の業界に限らず、人事領域の課題を包括的な解決策を提供したこれまでの実績をご紹介します。
お悩みに合わせた解決策をご提供いたします。
トランストラクチャは、人事の課題を把握し、
解決する3つのフェーズ
「調査・診断」「計画・設計」「導入・運用」に対応した、
それぞれのサービスを提供しています。




組織・人事の状況を多面的に定量分析し、問題・課題を見える化する組織・人事診断サービスをはじめ、人事制度設計、雇用施策、人材開発の領域で多彩なサービスを提供。分析や戦略構築から、施策の実践、得られた効果の検証までサポートを通じて、真に経営に貢献する人事コンサルティングを行います。
組織や人事の課題解決には、その背後にある要因を正確に見極めることが不可欠との思いから、トランストラクチャはデータ分析を基にした定量的なレポートを提供。客観的かつ精密な課題の見える化により、分析や戦略構築、施策を適切に実践。効果の検証も可能です。施策の効果測定や進捗管理にも役立ちます。
当社を起点に、人事システム、退職金、給与計算などの人事関連サービス専門企業との緊密なネットワークを形成。組織・人事に関わるほぼすべての分野に対する良質なサービスの提供が可能です。企業が抱える組織・人事分野のさまざまな課題をワンストップで解決します。
トランストラクチャのコンサルタントは、徹底した教育とナレッジの共有、品質管理により、人事コンサルティングの最新知識から当社のサービスに関する方法論・テクノロジーまで熟知しています。全分野を網羅する課題解決力で、お客様の組織の成長と変革に向けた持続可能な人事戦略と組織体制を構築します。
組織・人事制度導入後も、最少2名の経験豊富なコンサルタントが伴走。長期的かつ持続的な改善を支援します。これによりお客様の組織に対する深い理解を得られ、その組織文化やニーズに適した戦略や改革の提案が可能。組織の持続的な成長と成功を支える重要な要素です。

人口減少・少子高齢化、テクノロジーの進化、働き方とライフスタイルの変化など、かつて経験したことのない変化が生じる2030年を見据えた組織と人事の課題解決はお済みですか?まずは、貴社の現状をお聞かせください。

トランストラクチャについての会社情報やサービス利用のご検討に際して当社の資料が必要な方に役立つ各種資料はこちらからダウンロードが可能です。ご登録メールアドレス宛にご希望の資料をお送りします。

トランストラクチャのコンサルタントが執筆したコラムを掲載するたびに、あらかじめご登録いただいたメールアドレス宛に更新情報をご案内します。まずはお問い合わせフォームより購読希望をお知らせください。



トランストラクチャでは、人事の課題解決に役立つ具体的な事例や、
最新の人事トレンドを反映した無料セミナーを積極的に開催しています。



組織と人事に関する最新情報やノウハウを発信。
ビジネスの現場ですぐにでも役立つ内容を厳選してご紹介します。
人事に関する魅力的なデータやチャートを
分かりやすく解説します。
これらの情報は、将来の人事管理に向けた基盤を提供します。

2026.02.06
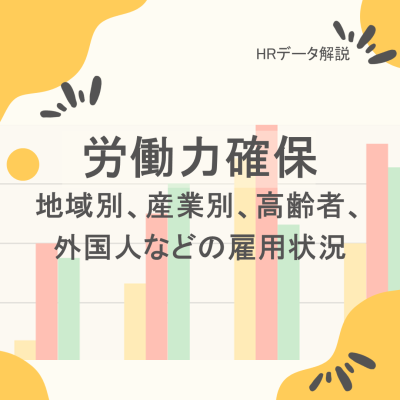
2026.01.23
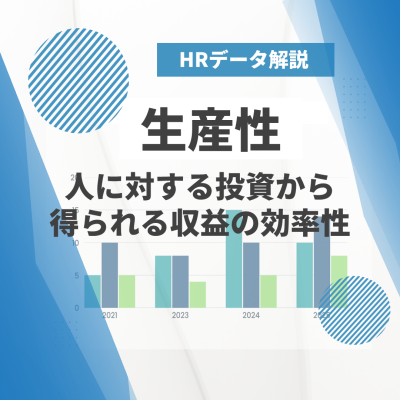
トランストラクチャのコンサルタントによるコラムをお楽しみください。
多くの企業様へのサポートを通じて蓄積された知識や、
日々の人事・経営に対する洞察をシェアします。

2026.02.16
ある国に、二人の営業マンが派遣された。現地では誰ひとりとして靴を履いていない。 ひとりは肩を落として言った。「ここでは靴は売れません。誰も靴を履いていないのです」。もうひとりは目を輝かせて言った。「ここには無限の需要があります。誰もまだ靴を履いていないのです」。 同じ現実を見ていながら、解釈がまったく異なるこの寓話はマーケティング領域で語られることが多いが、実は人事の本質を象徴している。なぜなら人事とは、「現状評価の仕事」ではなく、「未来可能性に価値を見出す仕事」だからである。 心理学では、出来事を別の枠組みで捉え直すことを「リフレーミング(Reframing)」と呼ぶ。裸足の国の二人の営業マンは、その違いを端的に示している。リフレーミングは現実を否定したり、美化したりする技術ではなく、“事実を変えずに意味づけを変える”視点である。人材開発の世界ではこれを「ポジティブ・アプローチ」と呼び、課題や不足の指摘よりも「今ある強み」「これからの可能性」に焦点を当てることで、人が行動するエネルギーを引き出す考え方として重視されている。 「裸足=市場がない」と捉えるか、「裸足=潜在的市場」と見るかで、未来は大きく変わるのである。 人事の現場にも、まったく同じ構造が存在する。企業では「若手が受け身だ」「管理職が育たない」「イノベーションが生まれない」といった声が聞かれることが多い。そのとき、「人材の質の問題」と断定するのか、それとも「学習機会や成長設計の不足」と捉えるのかで、施策の質も方向性も結果も大きく変わる。評価制度や育成施策が期待どおりに機能しない背景には、「足りない点」や「リスク」にばかり焦点が当たり、行動が生まれるデザインになっていないケースが少なくない。裸足を欠点と見るか、靴を履く未来の伸びしろと見るか、その違いが組織文化や価値観を決定づける。 さらに、社員が主体的に動かない状況に対して、「やる気がない」「意識が低い」と断じるのは簡単だ。しかし、彼らはただ、“履きたくなる靴”や“歩きたくなる道”を与えられていないだけなのかもしれない。人事の役割は、制度や仕組みといった「靴」を提供することだけではなく、「歩く理由」「歩き方」「歩きたくなる未来の景色」をデザインすることである。人は納得・成長実感・挑戦意欲が揃ってはじめて、自ら歩き出す。 そして、この寓話は多様性という現代の重要テーマにも通じる。裸足で生きる文化があるなら、それを否定するのではなく、「その文化に合った靴」を考える想像力が求められている。これは特定の価値観やキャリア観を全員に押しつけるのではなく、一人ひとりの強み・志向・歩幅に寄り添った機会設計を行うタレントマネジメントそのものである。 人材を「履いていない」と見れば組織は停滞し、「まだ履いていない」と見れば未来は開ける。ここには単なる言葉遊びではなく、人材マネジメントの思想的な分岐点が存在する。「できていない人」を減点評価するのか、「これからできる可能性を持つ人」として育成するのか。その違いは、組織文化、学習し続ける土壌、新しい挑戦が生まれる風土と直結する。可能性を前提に語れる組織は、失敗を学習資産へと転換し、また挑戦者を支援し、経験の差を機会の差にはしない。 現代の人事に求められているのは、制度の整備や数値管理に留まる役割ではなく、配置・評価・育成・制度といった機能を超え、個人の内側に眠る「未発火の価値」を見つけ、成長の道筋に光を当てる眼差しである。たとえ履いている靴が今はなくても、裸足で歩いてきた背景や、地面を感じてきた感覚にこそ、その人ならではの強みが潜んでいるかもしれない。能力は“保有しているか否か”の静的な概念ではなく、機会・意味付け・文脈によって引き出される“動的な資源”である。 だからこそ、歩き出すための一歩を「指示する側」ではなく、「ともに考え、設計し、支える側」でいられるかどうかが、人事の存在価値を大きく左右する。伴走者として寄り添える人事は、個人の成長物語に共に関与し、その人の未来に責任を持つ立場になる。成長とは与えられるものではなく、本人が歩き出す“納得の理由”と“希望の方向性”を得たときに初めて動き始める。その瞬間をつくることこそ、人事が果たす最大の価値ではないだろうか。

京都・龍安寺の石庭には、15個の石が一度にすべて見えないように配置されているという。 どこから見ても、必ず一つの石が「見えない」。 だがそれが逆に、庭に「奥行き」と「想像」を生む。そこに日本庭園の深さがある。 これは、組織構造にも似ている。 人事制度や組織設計を考えるとき、つい「完全な構造」「欠けのない制度」を目指したくなる。 でも、本当に人が活きる組織には、どこか「見えない石」がある。 すべてが説明できるわけではないが、なぜかうまく機能する。 そういう「余白」こそが、組織に深みと呼吸を与えるのではないだろうか。 人事の仕事をしていると、構造設計に対する「誤解」によく出会う。 「要員を増やしたら回るでしょ」 「とりあえずポジションをつくろう」 「課長が多すぎるから減らせばいい」 これらは部屋の間取りだけで家の快適さを決めようとするようなものだ。本当に大事なのは、 「どこに」「どんな人を」「どう配置するか」。 つまり、石庭でいえば「石をどこに置くか」である。 庭園の美しさは、石の個数ではなく、「石と石の間にある空間」で決まる。 それは組織でも同じだ。 例えば―― ・優秀な部下を、上司が「活かしきれない」構造 ・部門間に「壁」がある構造 ・中堅社員が「漂流」する構造 これはすべて、「配置の失敗」だ。 どれも石そのものではなく、「置き方」の問題である。 逆に、全体が生き生きと動く組織は、「余白」がある。 役職に意味があり、立ち位置に物語があり、個のスキルに応じた「置かれ方」がある。 それはまるで、絶妙な間隔で置かれた庭の石のようだ。 そして、もう一つ忘れてはならないのが「視点」だ。 庭をどう見るかは、立つ場所によって変わる。 同じ配置でも、視座が変われば、石の意味も変わる。 組織でも、上層部から見た構造と、現場社員から見た構造は別物だ。 役割や階層を「機能」として配置したつもりでも、現場から見れば「障壁」になっていることもある。 だからこそ、人事の仕事には「複数の視座」が欠かせない。 私たちはしばしば「人が足りない」という声を聞く。 だが、それは「石が足りない」問題ではなく、「石をどう置くか」の問題かもしれない。 一人ひとりの社員は、石そのもの。動かせば、見える景色が変わる。 構造改革とは、「石の総入れ替え」ではない。 一つの石を3センチずらすことで、全体の見え方が変わることがある。 それが人事の「設計力」だ。 人をただ「足す」のではなく、「活かす」。 その視点を持てるかどうかで、組織の風景はまるで違うものになる。 そして何より、人をどう配置するかは、単なるオペレーションではない。 その人をどう活かしたいかという、組織の意思の現れでもある。 石は、ただ置かれているのではない。 そこには、誰かの「意思」が宿っている。 だからこそ、組織設計には、美学と哲学が必要なのだ。 人をどう置くか。それは、人をどう見ているか、の表明でもある。

いま、多くの経営者や人事責任者が直面しているのは、「制度は変えたのに、行動が変わらない」という現実だ。理念を掲げ、人事制度を改定し、変革の旗を立てても、社員の行動が旧来のままでは成果は出ない。合理的には正しいのに実行が伴わない──その背景には、往々にして「組織文化」という見えない壁がある。 戦略がコモディティ化した時代、企業の差は“実行力”で決まる。短期的にはポジショニングや施策で優位を築けても、中長期的には実行力の強さが持続的な競争力となる。その実行力の源泉こそが、組織文化である。 モチベーションを高めるスローガンやキャッチコピーではなく、社員一人ひとりの心理の奥底に根づき、行動を生み出す“心理的エンジン”としての文化が、組織能力を競争優位へと高める鍵となる。 文化は、単なる「雰囲気」や「仲の良さ」ではない。シャインが示したように、それは組織の伝統や経験が刷り込まれ、儀式やシンボルを通じて共有され、最終的に社員の“無意識の前提”となるものである。 強い文化を持つ組織は、外部から見ても独自の個性が際立っている。一方、どこにでもあるような働き方が自然に行われているなら、その文化は弱い。強い文化ほど、社員にとって「当たり前」となり、もはや意識に上らない。だからこそ、社外の第三者からどう見えるかを診断することが重要だ。 よく混同される「組織風土」との違いも押さえておきたい。風土は、組織の心理的な基盤──活気がある、閉鎖的であるなど、良し悪しで語られる“土壌”である。 一方、文化はその上に根づいた価値観や行動様式であり、「良し悪し」ではなく「その会社らしさ」を形づくるものだ。風土が土壌なら、文化はそこに刻まれた“行動のDNA”に近い。 経営変革や人事制度の改定が機能しないケースでは、この文化の存在を軽視していることが多い。どんな施策も、最終的には「社員一人ひとりの行動が変わるかどうか」に行き着く。 だが、今の文化を診断せずに制度だけを変えれば、「言っていることは合理的だが、動かない」という現象が起こる。 まさに「仏作って魂入れず」だ。最も見落とされがちなのは、組織の最小単位である“上司と部下の関係性”である。そこに根づく行動の型こそが、組織文化そのものであり、行動変容の起点となる。 文化を変えるには、まず「現状の文化が何を是としているか」を把握し、そのうえで「変革後にどんな文化を浸透させたいのか」を描く必要がある。強い文化を持つ組織ほど抵抗も強い。 したがって、制度や施策を変えるのと同時に、文化をどう変化させるのかをマネジメントする必要がある。抵抗は必ず生じるため、変化を意図的に起こし、抵抗を最小限に抑え、社員の行動変容を導くことが有効である。 文化は、毎日の行動の積み重ねによってしか変わらない。キャッチフレーズを飾るより、社員が“自然にとる行動”が変わったとき、文化は動き出す。そして、その変化が実行力となって、企業を強くしていく。 出典:「エドガー・シャイン『組織文化とリーダーシップ』(原著タイトル: Organizational Culture and Leadership)」
私たちは「“見える化”を強みとした、
企業の持続的な成長・発展を後押しする組織人事コンサルタント」として、
日本社会が抱える多くの課題に向き合い、企業の未来を見据えています。

2025.12.16
2025.11.27
2025.10.28